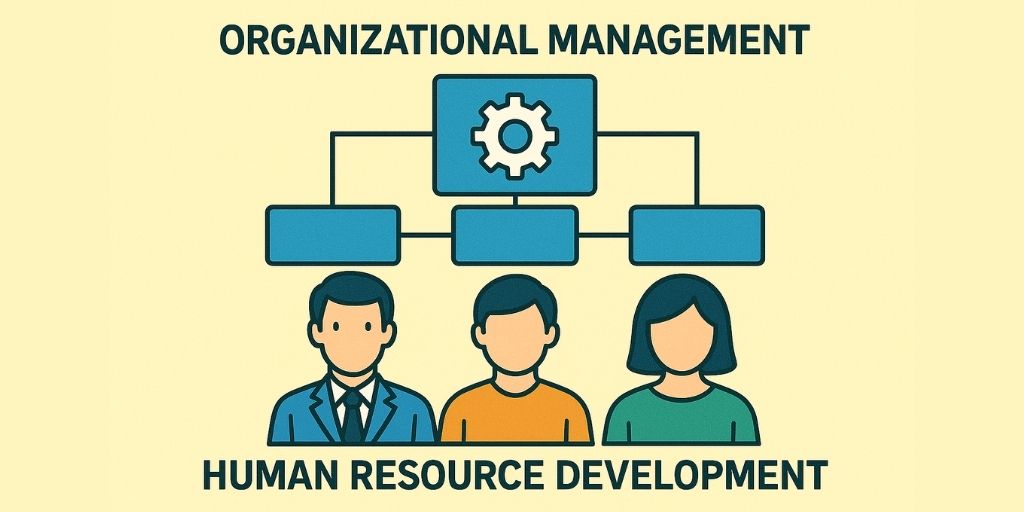「理・情・恐怖」ですが、これは有名な弁護士であった中坊公平氏が提唱されていた「正面の理・側面の情・背後の恐怖」のことになります。お聞きになったことはありますかね!?
この言葉を知ったのは、私が30歳のころでした。特に言葉の説明を聞くこともなく、直感的に「確かにこの3つだ!」と勝手に確信したのを覚えています。以来、様々な場面で自ら実践してきましたし、部下にもこれを伝えてきました。
この言葉については、すでに多くの方々が紹介されていますし、時代に即した解釈や解説などもされているので、いまさら感はありますが、これまでに私が人や組織のマネジメントの場面において「座右の銘」のようなものとしてきたこともあって、改めて紹介しておきたいと思います。
部下のマネジメントに迷っている方に是非ご一読いただきたいです。
本記事でわかること:
・人の行動タイプ(5タイプ)
・各タイプの人材に有効な働きかけ
・さらなる活用法
<筆者プロフィール>
・会社勤め35年、ITエンジニア
・大手IT企業・ITベンチャー・事業会社IT部門を経験
・事業責任者や部門長として、人材育成・採用・組織運営を長く経験
・個人事業主としても活動、マイクロ法人も設立・運営
人はいかにして動くか
仕事において人に動いてもらいたい場面は多くあります。
おもには部下に動いて欲しいことが多いと思いますが、場合によっては上司や他部門の関係者、お客様に動いてもらいたいこともあります。ここで言う「動く」は、何らかの仕事をする、何らかの役割を果たすといった意味です。
もしも動くことにメリットがあったり、結果として何か報酬があって、それを理解していると人は動きます。放っておいても動きます。
ですので、メリットや報酬が一見するとないなかで、人に動いてもらうにはどうすればよいか? それが「正面の理・側面の情・背後の恐怖」ということになります。
以下の内容は、中坊公平氏が意図していたことと少し異なるのかもしれませんが、私なりに解釈し実践し効果があった考え方になりますので、その文脈で話を進めます。
人は3つのタイプに分かれる
人は大まかに3つのタイプに分けることができます。
タイプ1:正論で動くタイプ
「この仕事には、◯◯◯な意味がある、実施するのは難しいが、必ずやる必要がある」などと、仕事の意義・必要性などについて正面から理にかなった説明をしたら、それを理解して自ら自律的に動き出す人
タイプ2:情で動くタイプ
仕事の意義・必要性などを説明したら理解はするものの、なかなか動きだせない、動き出しても途中でペースダウンしたり止まってしまうが、「やる必要があるとわかっていても、実際にやるのは大変だよね、一緒に頑張ろうよ」といった声掛けやフォローなど、横から情をかけると何とか動く人
タイプ3:プレッシャーで動くタイプ
それでも思うように動かないけども「もしやらなかったどうなるかわかるか」と、脅しに近いプレッシャーをかけて、恐怖心を煽ることではじめて動く人
このそれぞれの働きかけを「正面の理、側面の情、背後の恐怖」として私はやってきました。
部下の中で、この話を聞いてい自ら実践しても、あまりうまくできいない者がいました。様子を見ていると、主たる原因は「正面の理」の段階で相手に響いていないためでした。説得力に欠けるという感じでうまくいかない。やはり前提となるコミュニケーション能力は重要です。
理解し腹に落ちれば動く人、情けをかけられて動く人、プレッシャーをかけられるやっと動く人、これらのタイプをすべて動かせるのが「正面の理・側面の情・背後の恐怖」になります。
ちなみに、人のタイプとしては上記3つ以外にあと2つあると私は思っています。
タイプ0:スーパーエース
「正面の理」すら必要としないタイプ。今何が必要とされていて、何を実施すべきで、どんなレベルで達成せねばならないかを、自ら感じ取って考えて実行できる人。
タイプZ:組織に不要なタイプ
「背後の恐怖」でも動かない人です。事情が許すのなら、組織やチームから退場してもらうべきタイプの人です。これまでの経験では、組織の規模が大きくなると、残念ながらこのタイプの人が一定数いるように思います。
日本では企業が社員を解雇するのは難しいので、配置転換や場合によっては減給など、より大きなプレッシャーをかけるなどが必要でしょう。私も実際にやったことがあります…。
さらなる活用法
この方法は、3つのタイプのどれに当てはまる人なのか、あるいは追加の2つのタイプなのか、人を見極める方法としても使えます。その人とのより良い関係性を作っていく上でも、有益な洞察が得るきっかけになる手法です。
また相手によっては、「正面の理・側面の情・背後の恐怖」の種明かしをすることで、そこから気づきを得て成長することがありますので、人を育成する方法としても使えます。
様々な場面で効果的に使える手法ですので、活用しない手はないと思います。
まとめ
人が動くには、「正面の理・側面の情・背後の恐怖」という三つの働きかけが有効です。
タイプ1:物事の意義や必要性を筋道立てて説明すれば、自ら動き出す人がいます。これが「正面の理」です。
タイプ2:それでも動けない人には、寄り添いや励ましといった「側面の情」が支えになります。
タイプ3:どうしても動かない場合には、プレッシャーを与える「背後の恐怖」が最後の手段として効いてくることがあります。
加えて、特別な説明が不要なほど自律的に動ける人もいれば、逆に何をしても動かない人もいます。
大切なのは、その相手がどのタイプに当てはまるかを見極めたうえで、適切なアプローチを選ぶことです。
この考え方は、日々の仕事や部下育成、チーム運営の中で幅広く役立つはずです。
ぜひ実践してみてください。