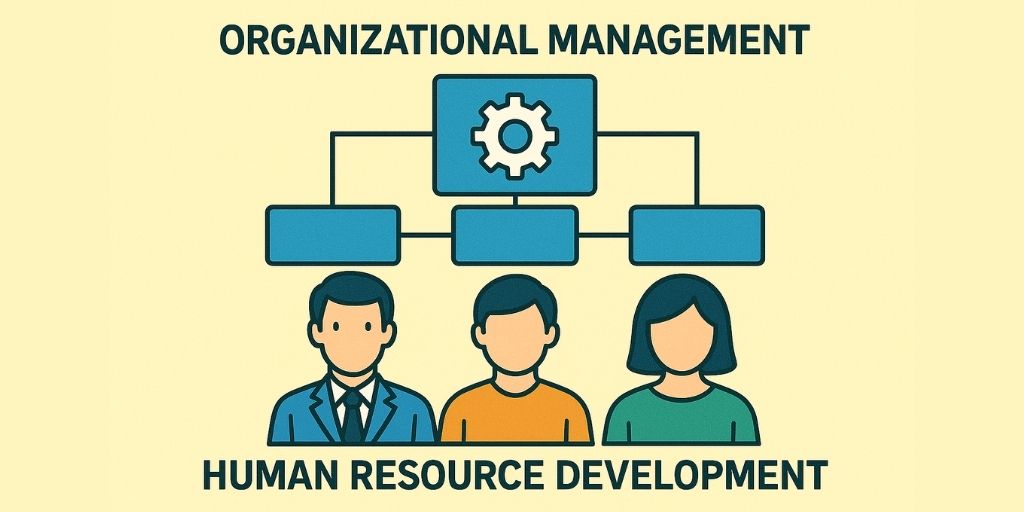アメリカのIT企業で働いていたときの経験から、日本との違いを強く感じたことが多々ありました。
特に印象的だったのは、アメリカ人ITエンジニアの職場でのふるまいの違い。同じ「ITエンジニア」という職種であっても、国が違えば価値観や行動パターンは大きく変わるという実感があります。
この記事では、実際にアメリカで約6年間働いた経験をもとに、日本との違いや気づきを紹介するとともに、近年日本でも注目されている「ジョブ型人事制度は必要か?」という問いについても、実感ベースで考察してみたいと思います。
アメリカのITエンジニアの働き方に興味のある方、ジョブ型人事制度に疑問を感じている方など、ご一読いただければ幸いです。
<筆者プロフィール>
・会社勤め35年、ITエンジニア
・大手IT企業・ITベンチャー・事業会社IT部門を経験
・海外プロジェクト経験 10年
・事業責任者や部門長として、人材育成・採用・組織運営を長く経験
・個人事業主としても活動、マイクロ法人も設立・運営
アメリカ人ITエンジニアの働き方
担当外でも助け合うマインド
アメリカのITエンジニアは、「自分の仕事じゃないから知らない」といった発言をすることは基本的にありません。
もちろん、担当外のことに積極的に関与しようとする訳ではないです。しかし、自分の仕事も担当外の仕事も関連していることを認識しているので、他人の担当でも普通に相談に乗ってくれたり、協力してくれます。これは当時の私にとってはカルチャーショックでした。もっとドライだと思っていたので。
このような行動は、日本のジョブ型人事制度が目指す「役割の明確化」とは逆のようにも見えますが、むしろ「ジョブ」を超えた自律的な動きこそが、成果を出す組織に必要な文化なのかもしれません。
ネガティブな言動を避ける文化
アメリカ人は公の場では基本的にネガティブなことを言いません。
それが人にどう受け取られるかに敏感で、自分の言動が否定的に捉えられることを極力避ける傾向を感じます。
ネガティブな言動をしていることで、その人の評価が下がることもあります。
おそらくこれは、子どものころからの教育の影響が大きいのではないかと思っています。
上司には忠実、ただし合わなければすぐ辞める
アメリカでは上司の判断で解雇されることもあるため、上司に逆らうような言動は基本的に見かけません。
上司の方針の中で最大の成果を出すよう努力しますが、逆に「合わない」と思えばすぐ辞めるのも普通の選択肢です。そして、仕事を辞める際には、引き継ぎなどは基本的に考えていません。対象の業務が極めて重要なものであれば、退職にあたって引き継ぎの準備を相談することはありましたが、基本的には後任者として採用されてくる担当者にすべてお任せになります。
なので、場合によっては後任者が着任する時点ですべてリセットなどということも多々ありました。
担当者が辞めたことによって業務が止まっても、会社も取引先もある程度それを許容する文化があるのも印象的でした。
日本においては引き続ぎなしに辞める人は少ないと思いますが、ジョブ型を導入するにあたっては、このような事態になることも想定が必要かもしれません。
フィードバックは「ハンバーガー方式」で
アメリカ人の部下に対しては、直接的なダメ出しは禁物です。
自尊心を傷つけると、その後のパフォーマンスに影響が出ることもあり、必ず「ポジティブ → 指摘 → ポジティブ」のハンバーガー方式で伝えるのが基本です。
これは現代の日本の人材マネジメントにおいても有効な手法です。おそらく組織全体のパフォーマンスが上がります。しかしながら、日本の年配の管理職にはこれができない人が多い気がして、非常に残念です。
日本でも最近はハラスメントの意識も高まっていて、ダメ出しというコミュニケーションは今後は減っていくのかもしれませんが。
残業はしない、でも家で時間外に働く
オフィスでの残業はほぼゼロ。しかし、家で残業している人は多いです。時間の使い方が柔軟で、自分の裁量で働くスタイルが定着しています。ジョブ型というよりも「成果重視」の文化が前提にあるため、いつどこで働くかよりも、成果をだしているかが評価につながる実感がありました。
技術者の気質は世界共通?
アメリカで働いていたチームでは、メンバーの多くはインド系やアジア系のエンジニアでした。彼らの気質は日本のエンジニアと似ていて、「新しい技術が好き」「手を動かして試すのが楽しい」「でもドキュメント作成は嫌い」「テストも嫌い」でした。エンジニアの特性というのは世界共通かもしれません。
複数の役割をこなすことが当たり前
私が参加していたプロジェクトは、新規事業の立ち上げプロジェクトで初期の体制は5名でした。
全員が一人で三役くらいの業務をこなさねば成り立たないベンチャー企業のような状況です。それぞれが自律的に動きながらも、全員がメンバーシップ型の働き方をしていました。
事業の立ち上げ時期という状況でしたので、ジョブ型など無縁の世界です。職務記述書には書ききれない。もしジョブ型のようなことをしていたらプロジェクトは失敗していたと思います。
ジョブ型人事制度は必要か?
最近日本では「ジョブ型人事制度」が話題ですが、実際にアメリカでも完全なジョブ型というわけではありません。環境や人材に応じてメンバーシップ型的な運用もされているのが実情です。
むしろ、アメリカで機能しているのは、個々の能力を前提にした柔軟な職務設計であり、「制度としてのジョブ型」ではなく、現場ごとの裁量と責任のバランスに支えられた文化だと感じます。
日本においても「制度ありき」でジョブ型を導入するのではなく、職場の実態や人材のタイプに応じた柔軟な運用こそが求められているのではないでしょうか。
まとめ
アメリカ人のITエンジニアと仕事をして感じたのは、役割を超えた協力、ポジティブなコミュニケーション、そして柔軟な働き方でした。文化や制度は異なっても、「チームとして成果を出す」「楽しく仕事をする」という価値観は共通しています。ジョブ型かメンバーシップ型かという制度論よりも、「どんな環境なら人は最大限の力を発揮できるのか」という視点が大切だと改めて実感しています。